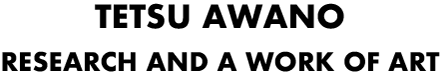大学学部在籍時より”無機能造形”と称して、「道具」としての有用な機能を持たない造形表現を現すことで、本質的な有用とはなにか、という研究・表現をしてまいりました。
当初は、キネティック・アート(動く彫刻)表現として現してきたものですが、研究と共にそれらをプロダクト・デザインの観点から見出すことで、より一般的かつ身近な目線で多くの人に理解しうる表現として現していくことになりました。
その研究・表現を”無機能造形”という当初考えた「道具」としての有用な機能を持たない観点から「道具」として”十分ではない”機能を持ったプロダクト・デザインという観点へとシフトし、更に「芸術(アート)」としての表現という観点も連関させることで、有用という本質を深部まで見出す研究・表現へと帰結させていったものです。
それらは「感覚覚醒補助具」と称し、博士論文においては「Press machine stand」「Flow machine stand」の2機で現しました。
「感覚覚醒補助具」は平易に申せば「気付き」の装置ということができます。真鍮やアルミニウム等によって表された機械的な表層は、人間らしさを強く拒絶するかのようですが、そこにこそ容易に現前としない見えざる真なる訴えかけが深層の記憶を触発させ、性急にではなく時間をかけ我々の心に気付きを呼び覚まさせると考えるものです。
「補助具」という意味は、上述したようにその装置の機能が十分ではなく、受容者との連関によって機能することを意味しています。この不可思議な「道具」から得られる形象や動きによって感覚の覚醒を促し、その気付きの差異が深層記憶を醸成させるとするところに本研究の「道具」としての本旨があります。